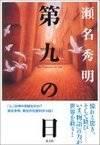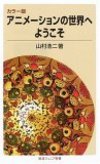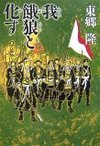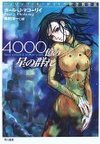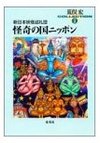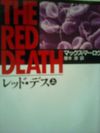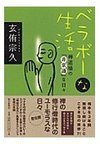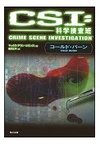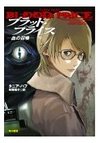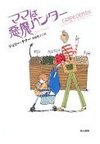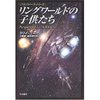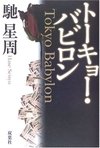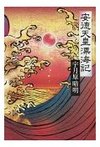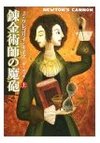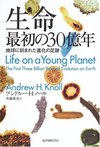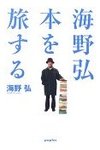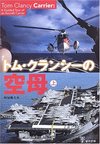@masatofujii
Blogを引越ししました。http://masatofujii-fujiigr.blogspot.com/変更よろしくお願いします。
書籍
2006-09-17
猫語の教科書 ポール ギャリコ
2006-09-17 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
楽園への疾走 J・G・バラード
2006-09-17 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
クリスマス・プレゼント ジェフリー・ディーヴァー
2006-09-17 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
闇を讃えて ホルヘ・ルイス ボルヘス
2006-09-17 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2006-09-12
でかした、ジーヴス P.G.ウッドハウス
2006-09-12 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2006-09-06
2006-09-05
「地球人のお荷物」「くたばれスネイクス!」「がんばれチャーリー」ポール・アンダースン、ゴードンR.ディクスン
2006-09-05 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (1) | トラックバック (0)
2006-09-01
2006-08-29
2006-08-24
我餓狼と化す 東郷隆
2006-08-24 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2006-08-22
2006-08-13
2006-08-11
あなたに不利な証拠として ローリー・リン ドラモンド
2006-08-11 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (1) | トラックバック (0)
2006-08-02
新日本妖怪巡礼団 怪奇の国ニッポン―荒俣宏コレクション 荒俣 宏
2006-08-02 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2006-07-30
ウィークエンド・ひーろー 放課後の英雄 火浦 功
2006-07-30 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
レッド・デス マックス マーロウ
2006-07-30 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2006-07-29
2006-07-28
僕、トーキョーの味方です―アメリカ人哲学者が日本に魅せられる理由 マイケル プロンコ
2006-07-28 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2006-07-25
CSI:科学捜査班 コールド・バーン マックス・アラン コリンズ
2006-07-25 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2006-07-20
2006-07-19
2006-07-17
2006-07-16
2006-07-11
ジョージ・R.R. マーティン
2006-07-11 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
リングワールドの子供たち ラリー・ニーヴン
2006-07-11 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2006-07-03
トーキョー・バビロン 馳星周
2006-07-03 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2006-06-28
2006-06-27
2006-06-23
コラプシウム ウィル マッカーシイ
 表紙が各所で話題になっているようですが、ハードSFです。しかし、どちらかといえば、スペース・オペラですね。不死身の超科学者が、超科学を使って慣性を無効にして高速宇宙船を作ったり、悪の科学者が太陽系を滅ぼそうとしたしたり、キャプテンヒューチャーそのままです。王制が復活し、社会科学や心理学は止まったまま。脳の可動パターンをすべて電磁的に保存できても、ほとんどの人は利用しようともしない。形態も人間のママ。しかし、スペース・オペラを、ハードSFで味付けして、こうすれば復活できるんだと示したことは凄い。いい意味で、伝統そのままに、読みやすく、共感しやすいライトノベル。これを、アレグレッサー・シックスの作者が書いたとは信じられません。★★★
表紙が各所で話題になっているようですが、ハードSFです。しかし、どちらかといえば、スペース・オペラですね。不死身の超科学者が、超科学を使って慣性を無効にして高速宇宙船を作ったり、悪の科学者が太陽系を滅ぼそうとしたしたり、キャプテンヒューチャーそのままです。王制が復活し、社会科学や心理学は止まったまま。脳の可動パターンをすべて電磁的に保存できても、ほとんどの人は利用しようともしない。形態も人間のママ。しかし、スペース・オペラを、ハードSFで味付けして、こうすれば復活できるんだと示したことは凄い。いい意味で、伝統そのままに、読みやすく、共感しやすいライトノベル。これを、アレグレッサー・シックスの作者が書いたとは信じられません。★★★
2006-06-23 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2006-06-20
2006-06-18
生命最初の30億年 地球に刻まれた進化の足跡 アンドルー・H.ノール
2006-06-18 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2006-06-14
2006-06-12
2006-06-11
啓示空間 アレステア レナルズ
2006-06-11 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2006-06-04
お腹召しませ 浅田次郎
2006-06-04 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2006-06-02
2006-05-31
2006-05-30
2006-05-29
カンブリア紀の怪物たち-進化はなぜ大爆発したか サイモン・コンウェイ・モリス
 タイトルだけ読むと、ワンダフルライフの継承本のようですが、実際は、バージェス頁岩の生物が、既存のどの門に入るかを分岐学的に考察した内容になっています。奇妙に見えるが決して新しい門が必要ではないことを、細かな形態を追うことで解説してあります。問題は、図や写真が少なく、細部にわたる形態の描写を延々と書かれてもイメージがわきません。他の本で形態を知っていなければ、まず読むことができないでしょう。文章も読みにくく、タイムマシンを使ってカンブリア紀の解説を行うにしては、環境情報が入らず、化石的形態の解説が続くなど、アンバランスな描写ばかりで内容の濃い割に、描き方の表現の下手さが目立つ本になってしまっています。★★
タイトルだけ読むと、ワンダフルライフの継承本のようですが、実際は、バージェス頁岩の生物が、既存のどの門に入るかを分岐学的に考察した内容になっています。奇妙に見えるが決して新しい門が必要ではないことを、細かな形態を追うことで解説してあります。問題は、図や写真が少なく、細部にわたる形態の描写を延々と書かれてもイメージがわきません。他の本で形態を知っていなければ、まず読むことができないでしょう。文章も読みにくく、タイムマシンを使ってカンブリア紀の解説を行うにしては、環境情報が入らず、化石的形態の解説が続くなど、アンバランスな描写ばかりで内容の濃い割に、描き方の表現の下手さが目立つ本になってしまっています。★★
2006-05-29 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2006-05-25
火札 十次郎江戸陰働き 庄司 圭太
2006-05-25 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2006-05-24
誰も知らなかった京都聖地案内 京都人が能楽にこめた秘密とは 小松 和彦
2006-05-24 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
宇宙クリケット大戦争 ダグラス・アダムス
2006-05-24 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
生命40億年全史 リチャード・フォーティ
 日本人の小学生が、掘られた近所の土から土器を見つけるように、イギリスでは化石を拾っていたらしい。植物学や、考古学が日常に生きている生活にとけ込んでいた。そんな幼少時代を交えながら、作者の考える生命史を語ったエッセイのような本であり、教科書のような本ではない。従って、ペルム紀はどんな時代だったのかなどと知識を早急に求める人にはなんて約に立たない本だと思われるかもしれないが、こういいった本こそ知識とは何か、生物史とはどういったものなのかを教えてくれるような気がします。読んでいて楽しく、名文でもあり、挿話もなかなか含蓄があります。こういった人が、おじさんにいればいいのにといった書籍でしょうか。★★★★
日本人の小学生が、掘られた近所の土から土器を見つけるように、イギリスでは化石を拾っていたらしい。植物学や、考古学が日常に生きている生活にとけ込んでいた。そんな幼少時代を交えながら、作者の考える生命史を語ったエッセイのような本であり、教科書のような本ではない。従って、ペルム紀はどんな時代だったのかなどと知識を早急に求める人にはなんて約に立たない本だと思われるかもしれないが、こういいった本こそ知識とは何か、生物史とはどういったものなのかを教えてくれるような気がします。読んでいて楽しく、名文でもあり、挿話もなかなか含蓄があります。こういった人が、おじさんにいればいいのにといった書籍でしょうか。★★★★
2006-05-24 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)