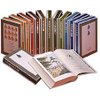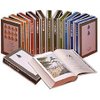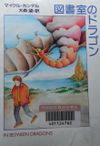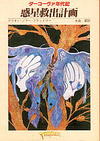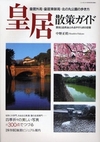@masatofujii
Blogを引越ししました。http://masatofujii-fujiigr.blogspot.com/変更よろしくお願いします。
書籍
2009-08-08
2009-08-07
2009-08-06
2009-08-05
2009-07-25
2009-07-24
2009-07-23
2009-07-21
2009-07-13
2009-07-12
2009-07-09
エヴァンゲリオンの夢―使徒進化論の幻影 大瀧 啓裕
 映画化話題の中、創元社のサイトで、この本をみつけてびっくりしました。大瀧啓裕といえば、ぼくの中では、フィリップ・K・ディック「ヴァリス3部作」の訳者であり、神秘主義の大家です。他にも、ラグクラフト、「悪魔の系譜」 ジェフリー・B. ラッセルや、「天使の世界」 マルコム ゴドウィンなどの神秘主義の古典的名著の訳者です。それが、テレビアニメの解説本を書くとは。早速、手に入れて読み始めると、いきなり、セフィーロートーの流出から解説が始まります。これには、笑いました。解説というより、エヴァンゲリオンを通じて、大瀧 啓裕世界が想像され、その範疇の中で、強引にアニメの解釈が行われているのがわかったからです。
映画化話題の中、創元社のサイトで、この本をみつけてびっくりしました。大瀧啓裕といえば、ぼくの中では、フィリップ・K・ディック「ヴァリス3部作」の訳者であり、神秘主義の大家です。他にも、ラグクラフト、「悪魔の系譜」 ジェフリー・B. ラッセルや、「天使の世界」 マルコム ゴドウィンなどの神秘主義の古典的名著の訳者です。それが、テレビアニメの解説本を書くとは。早速、手に入れて読み始めると、いきなり、セフィーロートーの流出から解説が始まります。これには、笑いました。解説というより、エヴァンゲリオンを通じて、大瀧 啓裕世界が想像され、その範疇の中で、強引にアニメの解釈が行われているのがわかったからです。
ぼくは、エヴァンゲリオンを見てないので、とりあえず、本の進行に合わせて、借りてきたDVDを見ながら読み進めました。映画版は、まだ見てないんですが、アニメを見ることさへ、この本を読むには必要ありません。フィリップ・K・ディックが、神秘体験を基にヴァリスを書いたように、エヴァンゲリオンを見るという体験を基に、翻訳家らしく、解説本を書いたといえるでしょう。アニメを楽しむ以上の、楽しみがここにあります。エヴァンゲリオン好きには申し訳ないですが、大瀧 啓裕がこういった本を書いたことを祝福し、読めることを幸せに思います。★★★★★
2009-07-06
2009-07-02
2009-06-27
2009-06-24
2009-06-22
2009-06-19
2009-06-18
ドラゴンズ・ワイルド ロバート・アスプリン
 アスプリンが死んでしまって残念ですが、遺作ということで早速読みました。マジカルアイランドのネガポジ版といったところです。主人公は、怠け者、夜型、遺伝でドラゴンの血を受け継いで、努力なしで、人を引き付ける力を手に入れます。しかし、性格はマジカルアイランドの主人公と同じ。人に力を行使するのが嫌いで、誠実、ぎりぎりまで我慢するが、イザというときはとんでもない力を発揮するという訳です。裏社会とのつながり、仲間の集め方もマジカルアイランド。ただ、主人公が万能の魅力を努力もなしに手に入れているせいで、話しが破たんしてます。それに、舞台がフレンチクオーターなのはいいのですが、復興支援のつもりか、美化されすぎて鼻につきます。全体的に、不自然な明るさが、どうにも嫌な感じでした。マジカルアイランドの流れから、共著の作家リン・ナイが引き継ぐ話もあるようですが、絶対読みたくないと思っているし(共著作品はまるでテレビゲームです)、出版されれば必ず読みたい作者が1人いなくなったのは、とても残念だし、最後の作品がこれだというのも残念でした。★★
アスプリンが死んでしまって残念ですが、遺作ということで早速読みました。マジカルアイランドのネガポジ版といったところです。主人公は、怠け者、夜型、遺伝でドラゴンの血を受け継いで、努力なしで、人を引き付ける力を手に入れます。しかし、性格はマジカルアイランドの主人公と同じ。人に力を行使するのが嫌いで、誠実、ぎりぎりまで我慢するが、イザというときはとんでもない力を発揮するという訳です。裏社会とのつながり、仲間の集め方もマジカルアイランド。ただ、主人公が万能の魅力を努力もなしに手に入れているせいで、話しが破たんしてます。それに、舞台がフレンチクオーターなのはいいのですが、復興支援のつもりか、美化されすぎて鼻につきます。全体的に、不自然な明るさが、どうにも嫌な感じでした。マジカルアイランドの流れから、共著の作家リン・ナイが引き継ぐ話もあるようですが、絶対読みたくないと思っているし(共著作品はまるでテレビゲームです)、出版されれば必ず読みたい作者が1人いなくなったのは、とても残念だし、最後の作品がこれだというのも残念でした。★★
2009-06-13
2009-06-12
養蜂記 杉浦 明平
 なんとなく、養蜂がブームです。「ハチはなぜ大量死したのか」の巻末には、趣味の養蜂マニュアルが。オライリーの雑誌makeの編集者も養蜂を始めたと書いてあります。インターネットで検索すれば、10万円程度で養蜂セットが蜂付きで購入できます。皇居も近いし、養蜂でもと考えて、まずは参考書探し。しかし、この本の著者、杉浦 明平さんといえば、岩波文庫の「レオナルド・ダ・ヴィンチの手記」の著者です。ぼくも、この本読んでます。実家の渥美半島に戻って、趣味の養蜂をやっていて、その記録です。読んでなるほどです。やはり蜂は生き物なので、適当に始めようでは務まりません。分蜂や、スズメバチ被害、考えるだけで大変そうな作業が山もりです。しかも、かなり花がないと蜂蜜をとるのも難しそうです。読んでよかった、とにかく自然と付き合うのは大変だと改めて再認識できました。★★★★
なんとなく、養蜂がブームです。「ハチはなぜ大量死したのか」の巻末には、趣味の養蜂マニュアルが。オライリーの雑誌makeの編集者も養蜂を始めたと書いてあります。インターネットで検索すれば、10万円程度で養蜂セットが蜂付きで購入できます。皇居も近いし、養蜂でもと考えて、まずは参考書探し。しかし、この本の著者、杉浦 明平さんといえば、岩波文庫の「レオナルド・ダ・ヴィンチの手記」の著者です。ぼくも、この本読んでます。実家の渥美半島に戻って、趣味の養蜂をやっていて、その記録です。読んでなるほどです。やはり蜂は生き物なので、適当に始めようでは務まりません。分蜂や、スズメバチ被害、考えるだけで大変そうな作業が山もりです。しかも、かなり花がないと蜂蜜をとるのも難しそうです。読んでよかった、とにかく自然と付き合うのは大変だと改めて再認識できました。★★★★
2009-06-09
2009-06-08
2009-06-06
オオバンクラブの無法者 アーサー・ランサム
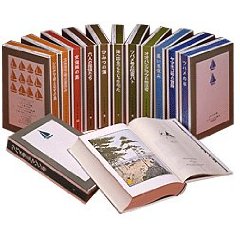 シリーズ5巻目です。今回は、お馴染みの4人兄弟+姉妹は登場しません。その代り、4巻で登場したディックとドロシアが活躍します。しかし、エミールと探偵たちみたいになってしまい、せっかくの船旅の持ち味が生かせてないようです。素晴らしい夏休みの復活を期待して、次巻を読みたいと思います。★★★
シリーズ5巻目です。今回は、お馴染みの4人兄弟+姉妹は登場しません。その代り、4巻で登場したディックとドロシアが活躍します。しかし、エミールと探偵たちみたいになってしまい、せっかくの船旅の持ち味が生かせてないようです。素晴らしい夏休みの復活を期待して、次巻を読みたいと思います。★★★
2009-06-04
2009-06-03
2009-06-01
2009-05-31
2009-05-28
2009-05-26
2009-05-25
2009-05-23
2009-05-22
2009-05-19
2009-05-18
2009-05-14
ペギー・スー 魔法の星の嫌われ王女 セルジュ・ブリュソロ
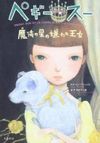 お父さんは、実は生きていて、役に立たない王様として登場。謎の妖精だったお母さんは、バカな王妃様に。王国を救おうと、ペギー・スーはひとり奮戦します。しかし、これほどの行動力があるのに、始めて会った父親になんとか会おうともしないし、真実を探そうともしない。普通、父親や母親と話すでしょう。話が矛盾だらけで、ついていけません。相変わらず大人は、役立たずですが、ストーリーだけが進んでいき、ストーリーに意味が見いだせません。作者は、自分の子供に読ませたい、子どもが好きになる女の子を作ろうと話を始めたはずですが、子どもがぐれてしまったのでしょうか?とにかく、完全な失敗作です。6巻ぐらいから、目立って構成力が落ちてきていましたが、とうとう破たんしたようです。1巻の素晴らしさが戻ってくることを期待します。★★
お父さんは、実は生きていて、役に立たない王様として登場。謎の妖精だったお母さんは、バカな王妃様に。王国を救おうと、ペギー・スーはひとり奮戦します。しかし、これほどの行動力があるのに、始めて会った父親になんとか会おうともしないし、真実を探そうともしない。普通、父親や母親と話すでしょう。話が矛盾だらけで、ついていけません。相変わらず大人は、役立たずですが、ストーリーだけが進んでいき、ストーリーに意味が見いだせません。作者は、自分の子供に読ませたい、子どもが好きになる女の子を作ろうと話を始めたはずですが、子どもがぐれてしまったのでしょうか?とにかく、完全な失敗作です。6巻ぐらいから、目立って構成力が落ちてきていましたが、とうとう破たんしたようです。1巻の素晴らしさが戻ってくることを期待します。★★
2009-05-13
2009-05-12
オッド・トーマスの霊感 ディーン・クーンツ
 世の中には恐ろしい小説というものがあって、そういった小説を書いた作家の小説をぼくは読まないようにしています。野坂昭如の「火垂るの墓」を読んで、野坂昭如を読むのをやめてしまったとか、そういったことです。この本も、そういった1冊になりました。確かに、すぐれた小説でしょうが、悲惨すぎます。1人称で書かれていることで、これからもっと恐ろしくなるような気がします。人間は、自分自身をも欺くことがあり、1人称をあえて選んだのは、そういった展開が待っているのではないでしょうか。霊が見えるのではなく、主人公はただただ気が狂っているだけかも知れないような気がします。シリーズのようですが、とにかくディーン・クーンツの本を読むのはやめることにしました。
世の中には恐ろしい小説というものがあって、そういった小説を書いた作家の小説をぼくは読まないようにしています。野坂昭如の「火垂るの墓」を読んで、野坂昭如を読むのをやめてしまったとか、そういったことです。この本も、そういった1冊になりました。確かに、すぐれた小説でしょうが、悲惨すぎます。1人称で書かれていることで、これからもっと恐ろしくなるような気がします。人間は、自分自身をも欺くことがあり、1人称をあえて選んだのは、そういった展開が待っているのではないでしょうか。霊が見えるのではなく、主人公はただただ気が狂っているだけかも知れないような気がします。シリーズのようですが、とにかくディーン・クーンツの本を読むのはやめることにしました。
2009-05-11
イスタンブールの毒蛇 ジェイソン・グッドウィン
 「イスタンブールの群狼」の続編です。甘かったミステリーのとしての完成度が一挙にあがり、ミステリーとしても、歴史小説としても十分に楽しめます。イスタンブールという街でなければ起きない犯罪、街自体が生み出す居心地のよさ、主人公の魅力、どれをとっても前作以上です。ちょっと年表整理。
「イスタンブールの群狼」の続編です。甘かったミステリーのとしての完成度が一挙にあがり、ミステリーとしても、歴史小説としても十分に楽しめます。イスタンブールという街でなければ起きない犯罪、街自体が生み出す居心地のよさ、主人公の魅力、どれをとっても前作以上です。ちょっと年表整理。
1571年 レパントの海戦
1789年 フランス革命
1826年 イェニチェリ廃止
1821年 ギリシア独立戦争
1829年 フェズ帽と表記されているトルコ帽など西洋式服装の導入
1839年 マフムト2世死去、アブデュルメジト1世即位
1839年 タンジマートの改革
ヤシムは、次作では、このタンジマートの改革に登用されそうな感じで今回は終わってますね。
マフムト2世の母、エイメ・デュ・ビュク・ド・リヴェリは、塩野七海の著書でおなじみです。ナポレオン・ボナパルトの皇后、ジョゼフィーヌ・ド・ボアルネの従妹といった伝説がありますが、どうもこれは伝説のようです。
2009-05-05
2009-05-04
王と最後の魔術師 エレン・カシュナー、デリア・シャーマン
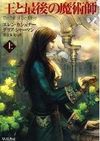 年代順に読んでみました。「剣の名誉」のジェシカも60代。今回は、剣は登場せず、消え去った魔法の復活が焦点になります。あとがきでは、アーサー王伝説のマリーンになぞらえてありましたが、どちらかというと、フレイザーの金枝篇でしょう。森の王になるには、2つの条件がある。1つは、枝。そして、2つ目の条件は王を殺すこと。そして、新しい森の王が復活し土地が蘇る。そんな王殺しの伝説と、儀式を執り行う魔術師が物語の根底にあります。しかし、あくまでも根底で、物語の98%は酒を飲んで、口げんかをし、実際に喧嘩になる学生と。学生にすぐに手をつけて、挙句に授業を休校する教授。甘やかされて、自分がやりたいことが分からず、飲んだくれ、服は破れて、記憶もなく昼まで寝ている貴族の若様というわけで、読んでるのがこれだけバカバカしい物語も珍しいです。しかも、上下巻。お酒をとったらなにも残らない、ダメ人間話が延々と続きます。最低の本でした。★
年代順に読んでみました。「剣の名誉」のジェシカも60代。今回は、剣は登場せず、消え去った魔法の復活が焦点になります。あとがきでは、アーサー王伝説のマリーンになぞらえてありましたが、どちらかというと、フレイザーの金枝篇でしょう。森の王になるには、2つの条件がある。1つは、枝。そして、2つ目の条件は王を殺すこと。そして、新しい森の王が復活し土地が蘇る。そんな王殺しの伝説と、儀式を執り行う魔術師が物語の根底にあります。しかし、あくまでも根底で、物語の98%は酒を飲んで、口げんかをし、実際に喧嘩になる学生と。学生にすぐに手をつけて、挙句に授業を休校する教授。甘やかされて、自分がやりたいことが分からず、飲んだくれ、服は破れて、記憶もなく昼まで寝ている貴族の若様というわけで、読んでるのがこれだけバカバカしい物語も珍しいです。しかも、上下巻。お酒をとったらなにも残らない、ダメ人間話が延々と続きます。最低の本でした。★