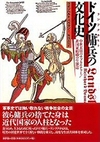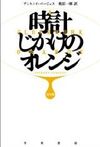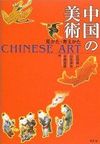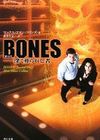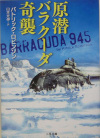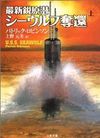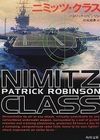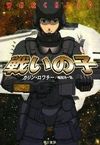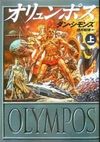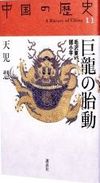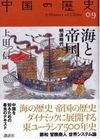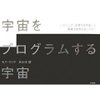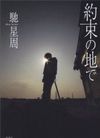@masatofujii
Blogを引越ししました。http://masatofujii-fujiigr.blogspot.com/変更よろしくお願いします。
書籍
2008-10-10
2008-10-09
未来喪失 佐藤 健志
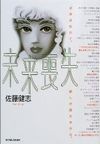 佐藤の健志初期の評論集で、ポピュラーカルチャーを分析した最後の本になります。中身をちょっとご紹介すると
佐藤の健志初期の評論集で、ポピュラーカルチャーを分析した最後の本になります。中身をちょっとご紹介すると
ジャン・ジロドゥ「パリ即興劇」
国民は強力な非現実を持たなければ偉大な現実生活持つことが出来ない
象徴的な言い方をすれば、ピンカートンに捨てられた蝶々夫人が自殺の道を選ばず、男装してピンカートンになりすますことで昇進を癒そうと試みたとき、宝塚歌劇は誕生したのだ
資源が枯渇する未来では、誰もが古いものを使いまわして再利用すると考え、「レトロ・フィット」(古物活用)なる概念をデザインの基本原則にしたという。←ブレードランナー
といった感じで、正しい間違ったではなく、どう分析するかです。そんな意味では最高に楽しい本になってます。6年ぶりに再読しました。★★★★
世界の測量 ガウスとフンボルトの物語。その後
ちょっと気になる誤植がありました。213ページ、最後から2行目 「監督が投石からガウスを」という部分。「監督が投石からフンボルトを」の誤植でした。ふたりをシンクロさせるために、わざとガウスになっているのかと思いましたが、出版社にメールすると、担当の方から凄く丁寧なメールをいただき、誤植であること、第2版では修正されていることを教えていただきました。ありがとうございます。増刷もかかって、12月にはケールマンの新刊が出るそうです。楽しみ、。
2008-10-02
世界の測量 ガウスとフンボルトの物語 ダニエル・ケールマン
 誤解している人が多いのですが、ポピュラーサイエンスの本ではなく、小説です。主人公は、天才数学者ガウスと、世界を測量したフンボルト。40ヶ国に翻訳され、「ダヴィンチ・コード」や「ハリー・ポッター」を押さえて、2006年世界のベストセラー第2位にランクされているそうです。ドイツで「ブリキの太鼓」と売上が比べられているというから、とんでもなく売れているのでしょう。実際、面白い。ガルシア・マルケスの「迷宮の将軍」を読んでる間ずっと思い起こしていましたが、後書きで本人も破格のリアリスムと唱えていることを知り納得しました。ポピュラー・サイエンスのフリをした伝奇小説とでもいえばいいのでしょうか?新しい小説の書き方であることは間違いありません。★★★★★
誤解している人が多いのですが、ポピュラーサイエンスの本ではなく、小説です。主人公は、天才数学者ガウスと、世界を測量したフンボルト。40ヶ国に翻訳され、「ダヴィンチ・コード」や「ハリー・ポッター」を押さえて、2006年世界のベストセラー第2位にランクされているそうです。ドイツで「ブリキの太鼓」と売上が比べられているというから、とんでもなく売れているのでしょう。実際、面白い。ガルシア・マルケスの「迷宮の将軍」を読んでる間ずっと思い起こしていましたが、後書きで本人も破格のリアリスムと唱えていることを知り納得しました。ポピュラー・サイエンスのフリをした伝奇小説とでもいえばいいのでしょうか?新しい小説の書き方であることは間違いありません。★★★★★
2008-09-30
2008-09-29
2008-09-28
2008-09-26
河鍋暁斎―逸話と生涯 大野 七三
カバーがついてなかったので、写真はなしです。伝説に飾られた河鍋暁斎の、やや客観的な伝記です。以外に真面目な実際の姿、知らなかった逸話と読み物としても十分です。★★★
2008-09-23
2008-09-21
2008-09-20
2008-09-17
2008-09-15
2008-09-14
2008-09-11
2008-09-10
2008-09-09
2008-09-07
2008-09-04
2008-09-03
2008-09-02
2008-09-01
2008-08-31
写真集 BONES 動物の骨格と機能美 湯沢英治
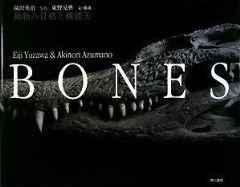 ぼくが唯一、写真集が出ると必ず見てるカメラマン・湯沢英治の最新作です。真っ黒なレイアウトの上に、白い骨が並びます。魚類から、哺乳類まで脊椎動物が持つ骨自体は、死んだものですが、生きているより、その機能を感じさせて、まがまがしく綺麗です。★★★★★
ぼくが唯一、写真集が出ると必ず見てるカメラマン・湯沢英治の最新作です。真っ黒なレイアウトの上に、白い骨が並びます。魚類から、哺乳類まで脊椎動物が持つ骨自体は、死んだものですが、生きているより、その機能を感じさせて、まがまがしく綺麗です。★★★★★