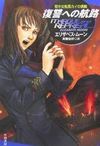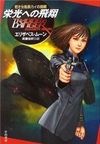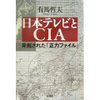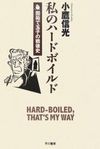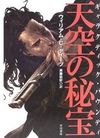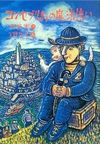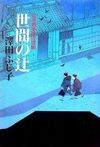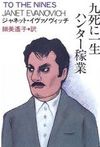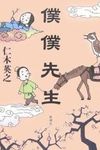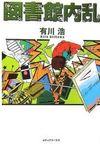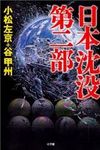@masatofujii
Blogを引越ししました。http://masatofujii-fujiigr.blogspot.com/変更よろしくお願いします。
書籍
2007-04-01
井沢式「日本史入門」講座 2 万世一系/日本建国の秘密の巻 井沢元彦
2007-04-01 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2007-03-31
復讐への航路 エリザベス・ムーン
2007-03-31 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2007-03-30
栄光への飛翔 エリザベス・ムーン
2007-03-30 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2007-03-29
2007-03-28
私のハードボイルド―固茹で玉子の戦後史 小鷹信光
2007-03-28 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2007-03-27
サンキュー、ジーヴス P.G. ウッドハウス
2007-03-27 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2007-03-26
天空の秘宝 ウィリアム・C・ディーツ
2007-03-26 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2007-03-25
2007-03-24
2007-03-23
コン・セブリ島の魔法使い 別役 実 スズキ コージ
2007-03-23 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2007-03-22
量子宇宙への3つの道 リー・スモーリン
2007-03-22 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2007-03-21
世間の辻 澤田ふじ子
2007-03-21 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2007-03-20
2007-03-19
2007-03-18
2007-03-17
2007-03-16
2007-03-15
街角のオジギビト とりみき
2007-03-15 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2007-03-14
2007-03-13
パピルスが伝えた文明―ギリシア・ローマの本屋たち 箕輪 成男
2007-03-13 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2007-03-12
太陽の簒奪者 野尻 抱介
2007-03-12 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2007-03-08
2007-03-07
2007-03-05
ウェブ人間論 梅田望夫・平野啓一郎
2007-03-05 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2007-03-01
中世ヨーロッパの書物 修道院出版の九〇〇年 箕輪成男
2007-03-01 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2007-02-28
2007-02-26
2007-02-25
「みんなの意見」は案外正しい ジェームズ・スロウィッキー
2007-02-25 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2007-02-22
エレキジャックその後
エレキジャック買ってはみたものの、記事を読んだだけになってました。問題は、PICです。エレキジャックは、PICの使用を前提に書かれています。ぼくは、PICを使ったことはないので、ライターも当然持っていません。WEBサイトのサポート頁には、メールを送って入手できるようですが、せっかくならと、秋月でPICライターのキットを買ってきましたが、今もそのまま。で、次号のエレキジャックは、PIC入門の記事が入っているようです。これを組み立てるのは、この記事を読んでからにしようということで、電子工作の道はまだまだ遠いです。
2007-02-22 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2007-02-18
ローマ人の物語 15 塩野 七生
2007-02-18 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2007-02-15
名誉王トレントの決断―魔法の国ザンス〈17〉 ピアズ アンソニイ
2007-02-15 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2007-02-12
2007-02-11
2007-02-06
2007-02-02
2007-01-30
デジタルデバイド
 梅田望夫著、「ウェブ進化論 本当の大変化はこれから始まる」はWEB2.0は実在するんだ、その正体はこれだってばっちり書いたすばらしい本です。ぼくも、書店に並んですぐに読みました。今回は、書評じゃなくて、この本が図書館に置いてあるのを見たという報告なんです。
梅田望夫著、「ウェブ進化論 本当の大変化はこれから始まる」はWEB2.0は実在するんだ、その正体はこれだってばっちり書いたすばらしい本です。ぼくも、書店に並んですぐに読みました。今回は、書評じゃなくて、この本が図書館に置いてあるのを見たという報告なんです。
そりゃ図書館にも置くでしょということはなくて、予約がいっぱいで図書館の棚に並ぶなんてありえないんです。ちなみに、文京区の図書館では51人待ち、港区67人。1人が2週間借りるとすると、50人で140日、3ヶ月以上の待ちになります。ぼくが見たのは、実家の広島県福山の図書館。四十九日の法要で帰ってます。(明日、東京へ帰ります)棚に並べてありました。もちろん、福山でもインターネットからの図書の予約はやっています。ハリポタなどは、東京都変らない予約数です。開発者の数の違い?でも、開発者ならAmazonで買うでしょうし、この予約数の差はなんなんだろう???
2007-01-30 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2007-01-28
2007-01-27
2007-01-26
2007-01-24
2007-01-23
図書館戦争 有川浩
 内容は、単純な女の子の成長物語ですが、舞台が図書館。しかも、本好きなら、まず知っている「図書館の自由に関する宣言」を拡大解釈して、本好きの痛いところをついた内容。
内容は、単純な女の子の成長物語ですが、舞台が図書館。しかも、本好きなら、まず知っている「図書館の自由に関する宣言」を拡大解釈して、本好きの痛いところをついた内容。
第1 図書館は資料収集の自由を有する。
第2 図書館は資料提供の自由を有する。
第3 図書館は利用者の秘密を守る。
第4 図書館はすべての検閲に反対する。
図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまでも自由を守る。
この自由を守るために、図書館が軍隊を持ちます。★★★★
それと、「図書館の自由に関する宣言」は上記が全文ではありません。こちらに全文があります。
2007-01-23 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2007-01-22
2007-01-20
2007-01-19
霊柩車の誕生 井上 章一
 この1ヶ月お葬式の起源や、しきたりの起源、お墓の起源などの本を手当たり次第に読みました。それで、どれも本当に新しい様式で、せいぜい江戸時代、酷いのは明治になってということがわかりました。だから、昔からこんなことをやってきたわけではなく、勝手にやってもいいんだと身に染みてます。そんな中で飛びきり面白かったのがこの本です。
この1ヶ月お葬式の起源や、しきたりの起源、お墓の起源などの本を手当たり次第に読みました。それで、どれも本当に新しい様式で、せいぜい江戸時代、酷いのは明治になってということがわかりました。だから、昔からこんなことをやってきたわけではなく、勝手にやってもいいんだと身に染みてます。そんな中で飛びきり面白かったのがこの本です。
霊柩車って、車なので、新しいシステムです。その前は、葬儀の会場からお墓まで葬送の列を組んでみんなで歩いたんですね。江戸時代はそれも、汚れなので夜に歩いた。さすがに都会ができると、そんな葬送の群衆は邪魔にしかなりません。そこで作られたのが霊柩車。
しかし、あのデカイ屋根はどうしてできたのか、そんな風俗的な感覚で霊柩車のキッチュな誕生を読み解いた本です。★★★★
2007-01-19 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2007-01-15
2007-01-14
魔法の国ザンス(16) ナーダ王女の憂鬱 ピアズ・アンソニイ
2007-01-14 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2007-01-12
書物の宇宙誌―澁澤龍彦蔵書目録
2007-01-12 カテゴリー: 書籍 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)